「うちの子、ChatGPTで宿題やってるみたい…これって大丈夫なの?」
もしかして、あなたも同じような不安を抱えていませんか?
私もつい先日、中学生の息子が「作文の宿題、AIに手伝ってもらった」と何気なく言った時、正直ドキッとしました。便利だとは思うけれど、これで本当にいいのか…そんなモヤモヤした気持ち、よくわかります。
今、私たち親は歴史上類を見ない判断を迫られています。
子供にAIを使わせるか、使わせないか。この選択が、子供の将来を大きく左右するかもしれないのに、正解なんて誰も教えてくれない。
実際、周りの親御さんと話していても、この話題になると途端にざわつきます。「うちは絶対使わせない」という方もいれば、「もう使わせ始めてる」という方も。でも、みんな共通して言うのは「正解が分からない」ということ。
私自身は、ChatGPT、Claude、Gemini、NotionAI…10種類以上のAIを仕事や副業で使い分けて、作業効率を3倍以上にアップさせてきました。文章生成からスケジュール管理、図解作成まで、AIを駆使することで収益も大幅に向上させた経験があります。だからこそ、AIの可能性も限界も、両方をリアルに理解しているつもりです。
この記事では、そんな私が実際に小中学生の子供を持つ親として悩み抜いた末に出した結論と、その過程で気づいた「洗濯機理論」について正直にお話しします。AIを使わせる派・使わせない派、どちらの気持ちも痛いほど分かるからこそ、両方の視点から徹底的に掘り下げました。
あなたが読み終わる頃には、きっと「我が家なりの方針」が見えてくるはずです。そして何より、「親として間違っていない選択をしている」という確信を持てるようになるでしょう。
最後には、同じように悩んでいる親御さんたちと一緒に考えたい重要な問いかけもご用意しています。一人で悩まず、みんなで答えを見つけていきませんか?
AI格差の時代到来
ここ数か月、生成AIの進歩はめまぐるしく、AIに関するコンテンツや高額な稼ぎ方教材があふれています。今や生成AIを使える人と使えない人では相当な格差が生まれてくるだろうと実感しています。
私自身は文章生成、画像生成、タスク管理などでAIを活用し、それぞれの癖や使い分けが分かってきました。中学2年の息子と小学5年の娘がいる親として、この子たちが大人になる頃にはAIを使うことが当たり前になり、使えないと大きく遅れを取ることになると確信しています。
でも、ここで正直に告白します。
実は周りの親御さんたちと、この話題について深く話し合ったことって…ほとんどないんです。PTAの集まりでも、習い事の送迎でも、生成AIの話なんて一度も出たことがありません。
みんな「ChatGPTって名前は聞いたことあるけど…」レベルで、実際に使いこなしている親なんて皆無に近い状況。だからこそ、今から子供にAIを使わせておけば、一歩も二歩もリードできるんじゃないかと思っているわけです。
「でも、それって本当に正しい判断なの?」
そんな自問自答を繰り返しながら、私が直面しているのが「子供に生成AIを使わせるべきか、使わせないべきか」という葛藤です。
AIが分からない方へ:生成AIとは、ChatGPTのように人間が質問すると自然な文章で答えてくれるコンピューターのことです。「○○について教えて」と聞けば、まるで人間のように説明してくれます。
AIを「使える人」と「使えない人」の決定的な差
表面的な使用で終わる人たち
多くの人は「○○について文章を書いて」という単純な指示で止まってしまいます。すると平気で嘘が混じった、いかにもAIらしい文章が出力され、「AIは使えない」と諦めてしまうのです。
実際、私の会社の同僚も「ChatGPTに『営業メール書いて』って言ったら、変な敬語だらけで全然使えなかった」と愚痴をこぼしていました。でも、それって当然なんです。相手の情報も、商品の詳細も、何の背景情報も与えずに「書いて」って言われても、AIだって困りますよね。
使いこなせる人の特徴
しかし使い込んで慣れてくれば、何度もやり取りを重ねながらプロンプト(AIへの指示文のこと)を調整することで、1000文字程度でも思い通りの自然な文章を生成できるようになります。
私の場合、副業で書いているブログ記事も、最初は「ブログ記事を書いて」と雑に頼んでいました。でも今では:
「30代の共働き夫婦をターゲットに、時短料理のメリットを伝える1200文字のブログ記事を書いて。体験談を交えて、親しみやすい口調で。見出しは3つに分けて」
こんな風に具体的に指示すると、もうほとんど手直し不要のレベルで仕上がってきます。
この差こそが、AI時代の格差の根源だと思います。
だからこそ、子供のうちにAIの使い方に慣れ、その限界や苦手分野を理解することが重要だと考え、少しずつ子供たちにもAIを使わせています。
具体的には、息子(中2)には「今度の社会のレポート、AIに聞いてみたら?でも出てきた答えが本当に正しいか、教科書でも確認してね」と声をかけたり、娘(小5)には「読書感想文のアイデア、AIに相談してみる?」と提案したりしています。
「プロンプトって何?」と思った方へ:AIに指示を出すときの「質問文」や「お願い文」のことです。この書き方次第で、AIの回答の質が大きく変わります。料理で言えば「レシピ」のようなものですね。
でも、ここで新たな不安が生まれるんです…
便利すぎることへの深刻な懸念
思考力の退化への不安
一方で、弁論大会の文章や標語をAIに作らせている光景を見ると、自分で考える脳が鍛えられないのではという懸念が同時に湧き上がります。
実際、先日息子が「明日までに読書感想文書かなきゃ」と言った時、私は思わず「AIに聞いてみたら?」と言いそうになって、慌てて口をつぐみました。これって、親として正しい反応だったのでしょうか?
娘も最近、算数の運動会の旗の図案を考えてくる宿題が出ると「おとうちゃん、LINEのAIに聞いていい?」と言ってくるようになりました。確かに案はすぐにたくさん提案してくれるけれど、自分で試行錯誤する時間を奪っているような気がして…。
創造性への影響
AIにイラストを描かせることに慣れてしまうと、自分で描くスキルが育たない。絵を描くスキルが壊滅的な大人(まさに私のことですが)は、もうAIに頼りっきりです。
これって、ちょっと怖くないですか?
今イラストが得意な人も、子供時代にAIがあったら描ける大人になっていなかったかもしれません。私の友人で、めちゃくちゃ絵が上手な人がいるんですが、彼女は「小学生の頃、暇さえあれば絵を描いてた」って言うんです。
でも今の子供たちは、暇があればスマホでゲームかYouTube。絵を描く時間なんてほとんどない。そこにAIまで加わったら…?
「でも、AIって本当にそんなにすごい絵を描けるの?」と疑問に思った方へ:実は今のAI、プロのイラストレーターレベルの絵を数秒で作り出します。私も仕事で使ってますが、正直「これ人間が描いたの?」って驚くレベルです。
ただ、ここで一つ思い出したことがあります。
そういえば、この前義母が「最近の若い人は地図が読めない」って愚痴をこぼしてたんです。「カーナビやスマホの地図アプリに頼りっきりで、方向感覚がない」って。
確かにその通りかも。私だって、カーナビなしで知らない場所に行くなんて考えられません。でも、だからって困ってますか?逆に、効率よく目的地に着けて便利じゃないですか?
道路地図を読み解くスキルは確実に退化しましたが、その代わりに私たちは「どのルートが一番早いか」「渋滞を避けるにはどうするか」という新しいスキルを身につけました。
うまく地図を読むことが出来るスキルを持っている人よりもナビをうまく使いこなすことが出来る人の方が、知っている土地でも知らない土地でも同じように、より早く目的地にたどり着けるんです。
技術革新とスキルの変遷 – 私の「洗濯機理論」
歴史が示すスキルの価値変化
写真が存在しなかった時代、リアルな絵を描けることは貴重なスキルでした。肖像画を描ける人は、まさに今でいう「インスタグラマー」みたいな存在だったんじゃないでしょうか。
しかし写真の登場で、いくら上手な絵でも「まるで写真のよう」という褒め言葉が限界となりました。逆に写真では表現できない非現実的な宗教画や抽象画は価値を保ち続けました。
ちょっと脱線しますが、ここまで書いていて思い出したのが、私の祖母の話です。祖母は戦後間もない頃、村で唯一「字が上手に書ける人」として、結婚式の席札や看板の文字を頼まれる仕事をしていたそうです。当時は今みたいに印刷技術が発達してなかったから、手書きの美しい文字は本当に貴重だったんですって。
でも今は?パソコンで美しいフォントを選んで印刷すれば、誰でも綺麗な文字を作れます。祖母の特技は、確実に「時代遅れ」になってしまいました。
「洗濯機理論」で考える技術受容
私が勝手に名付けた「洗濯機理論」では、洗濯機が普及し始めた頃、きっと「便利だけど手洗いほどきれいにできない。これに慣れると手洗いスキルが育たず、家事のできない人になる」という懸念があったはずです。
想像してみてください。大正時代のお母さんたちが井戸端会議で「最近の若い奥さんは洗濯機なんて使って…手洗いの良さが分からないのかしら」なんて話していたかもしれません。
しかし今、手洗いをする人はほとんどおらず、洗濯板を持つ家の方が特別です。洗濯板を使う技術を磨くより、洗濯機を使いこなし、その限界を理解して洗剤や部分的な手洗いを使い分けるスキルを身につける方が、結果的に家事上手への近道だったのです。
実際、私の母なんて洗濯機の設定を使い分けるのがめちゃくちゃ上手で、「この素材はこのコース」「この汚れにはこの洗剤を足して」って、まるで洗濯機のソムリエみたいです。
これは未来になってはじめて分かることなので、当時は大きな葛藤があったと思います。
「洗濯機理論って何?」と思った方へ:新しい技術が出てきた時、古いスキルが不要になることを恐れるより、新しい技術を使いこなすスキルを身につける方が結果的に有利になる、という私の考えです。ちょっと大げさに「理論」って名前つけちゃいました(笑)
そして今、私たちは同じ分岐点に立っているんじゃないでしょうか?
スキルの価値変化の具体例
失われたスキル・新たに生まれたスキル
洗濯機理論をもう少し具体的に見てみましょう。私たちの身の回りでも、こんな変化が起きています。
地図を読むスキル → カーナビやスマホの地図アプリを使いこなすスキル
私の父は今でも「紙の地図の方が全体が見えて分かりやすい」と言いますが、正直もう時代遅れですよね。今の子供たちは「Googleマップで最短ルートを調べて、リアルタイムで渋滞情報をチェックして…」なんて当たり前にやってます。
辞書を引くスキル → 検索スキル
昔は「辞書を引く速さ」が勉強の効率を左右しました。でも今は「どんなキーワードで検索すれば欲しい情報が見つかるか」の方がよっぽど重要。息子なんて、私が知らない英単語の意味を3秒で調べてきます。
暗記スキル → 情報を整理・活用するスキル
昔は「百人一首を全部覚えてる」とか「円周率を100桁言える」とかがすごいとされました。でも今は、膨大な情報の中から必要なものを見つけて、それを組み合わせて新しいアイデアを作る方が価値がある。
必須スキルから娯楽・特技への変化
面白いのは、完全に消えるわけじゃないってことです。
手紙を書く技術 → メールやLINEが主流となり、手紙は特別な味わいを演出する手段に
今でも手書きの手紙をもらうと嬉しいですよね。でも「手紙しか書けない人」だったら、逆に困るはず。
料理を一から作るスキル → 冷凍食品やミールキットを上手に活用するスキル
私の祖母は「最近の人は冷凍食品ばかりで…」と嘆きますが、共働きの私にとっては冷凍食品は救世主。むしろ「どの冷凍食品が美味しいか」「どうアレンジすれば手作り感が出るか」を知ってる方が、現実的に役立ちます。
そろばんを弾くスキル → 電卓やエクセルを使いこなすスキル
私たちの親世代は「そろばん3級」とか誇らしげに言いますが、今の時代にそろばんができても…ねぇ?でも数字に強いことの価値は変わってない。ただ、その「強さ」の定義が変わっただけ。
「でも、基礎的なスキルは大事でしょ?」と思った方へ:もちろんそうです!ただ、「何が基礎で何が応用か」の境界線が時代と共に変わっているんです。今の「基礎」は、昔の「応用」だったりするんですよね。
これらは「絶対に必要なスキル」から「できたらすごいスキル」に変化したのです。
でも、ここで気になることがあります。じゃあ、AIが普及したら、「文章を書くスキル」や「考えるスキル」も同じ道をたどるんでしょうか?
私の現在の考え方 – 新しいスキルへの適応
時代の流れを受け入れる選択
スキルの価値がスライドしていくのは時代の自然な流れです。いち早く新しいスキルを身につけることこそが必須だと考え、私自身もそう行動しています。
正直に告白すると、もう漢字を覚えることは当の昔に諦めました。「憂鬱」とか「薔薇」とか、もう絶対に手では書けません(笑)。でもスマホがあれば一瞬で変換できるし、困ったことは一度もありません。
その代わり、私が身につけたのは「どんな文章を書きたいか」を明確にイメージして、それをAIに的確に伝えるスキル。これって、実は昔ながらの「文章構成力」や「論理的思考力」が必要なんです。
AIは確実に進歩し続けるため、AIを使うこと自体が絶対に必要なスキルになることは間違いありません。
実際、私の副業収入も、AIを使い始めてから3倍になりました。文章生成のChatGPT、画像作成のMidjourney、資料作成のNotionAI…それぞれの得意分野を理解して使い分けることで、一人でできる仕事の幅が格段に広がったんです。
現在進行形の葛藤ポイント
でも同時に、今の私にライティングスキルや編集スキルがあるからこそ、AIを使いこなせている側面もあります。
例えば、AIが書いた文章を読んで「この部分は不自然だな」「ここは事実と違うかも」って気づけるのは、自分自身で文章を書いてきた経験があるから。自分で書く経験も必要だと感じています。
ここが今の私の最大の葛藤ポイントです。
先日、息子が「作文の宿題、AIに下書きしてもらっていい?」と聞いてきた時、私は5分くらい悩みました。
許可した場合のメリット:
- AIとの対話スキルが身につく
- 効率的に宿題を終わらせられる
- 「文章の型」を学べる
許可した場合のデメリット:
- 自分で考える時間が減る
- 文章力が身につかない
- 依存してしまう可能性
結局、「AIに下書きしてもらうのはOK。でも、必ず自分の言葉で書き直して、体験談は自分で考えて」という条件付きでOKしました。
もしかしたら私達のライティングスキルをはるかに凌駕するほどにAIが進歩すれば、そんなスキル自体が全く不要になるかもしれません。
子どもにAIを使わせるか使わせないか、「バランスが重要」という意見も多いでしょうが、隣に便利なものがあると分かっていれば、どうしてもそちらを使ってしまうのが人間だと思うんです。
「AIに依存しすぎるのが心配…」と思った方へ:その気持ち、すごくよく分かります。でも、電卓に依存して暗算ができなくなったからといって、今の私たちが困っているでしょうか?依存することと、使いこなすことは違うのかもしれません。
実は、つい最近こんなことがありました…
私たちが今、歴史の分岐点に立っている
実は、つい最近こんなことがありました。
娘(小5)が友達の家に遊びに行った時、その子のお母さんから「○○ちゃん、すごく検索が上手ですね」と言われたんです。詳しく聞くと、友達が宿題で困っていた時に、娘が「こういうキーワードで調べてみたら?」とアドバイスして、一緒に答えを見つけたんだとか。
その時私は、「あ、これが新しい時代の『勉強ができる子』なのかも」と思ったんです。
昔は「知識をたくさん覚えている子」が頭がいいとされました。でも今は「必要な情報を素早く見つけて、それを使って問題を解決できる子」の方が価値があるのかもしれません。
私たち親が今直面している選択は、まさに洗濯機が普及し始めた時代の人々が感じていた葛藤と同じかもしれません。
「子供に生成AIを使わせるべきか、子供のうちはAI一切使わせずに自分で考える力を伸ばすべきか」
この答えは、おそらく10年後、20年後になってはじめて「正解」が分かるものでしょう。でも、その時を待っていては手遅れかもしれません。
周りの親はまだ気づいていない
冒頭でもお話ししましたが、正直なところ、周りの親御さんでAIの可能性に気づいている人はほとんどいません。
先日、息子の友達のお母さんと話していて、「最近ChatGPTって流行ってるらしいですね」と言われました。でも話を聞いてみると、使ったことはおろか、どんなことができるのかも全然知らない様子。
「へー、便利そうですね。でも子供には使わせない方がいいですよね?」
そんな反応でした。
つまり、今AI教育を始めている家庭と、まだ何もしていない家庭の差は、想像以上に大きくなっているんです。
まるで、インターネットが普及し始めた1990年代後半のような状況。あの時も「ネットなんて危険だから子供には触らせない」という家庭と、「これからはネットの時代だから早めに慣らそう」という家庭に分かれていました。
結果はどうだったでしょうか?
「でも、AIって本当にそんなに重要になるの?」と疑問に思った方へ:私も最初はそう思っていました。でも仕事で使い始めて実感したのは、これは「便利ツール」のレベルを超えているということ。まさに「第二の検索エンジン」、いや「第二の言語」と言ってもいいかもしれません。
あなたの選択が子供の未来を決める
私は現在「早めにAIに慣れさせる」方向に舵を切っていますが、正直なところ、まだ迷いもあります。
息子は最近、LINEのAI機能を使って英語の宿題の分からない単語を調べています。1日の利用回数に制限があるので使いすぎることはないのですが、見ていると本当に効率的。単語の意味だけじゃなく、例文も教えてくれるし、発音も確認できる。
娘の方は、図工の時間に「どんな絵を描こうかな」と迷った時、AIに「小学生が描きやすい風景画のアイデア」を聞いて参考にしたりしています。
でも、ひとつだけ確信していることがあります。
それは、この選択を他人任せにしてはいけないということです。学校が決めてくれる、社会の流れに任せる、みんながやっているから…そんな受け身の姿勢では、子供の未来に責任を持てません。
学校教育の現実
実は先日、息子の担任の先生と個人面談があったので、恐る恐るAIについて聞いてみました。
「最近、生成AIについて学校ではどんな方針なんですか?」
先生の答えは…「そうですね、まだ具体的な指針は出ていないんです。とりあえず宿題では使わないように、とは言っていますが…」
つまり、学校現場でもまだ手探り状態。これが現実なんです。
だからこそ、各家庭が自分なりの方針を持つことが重要。学校の方針を待っていたら、子供の貴重な時間がどんどん過ぎてしまいます。
10年後の世界を想像してみてください
息子が大学生になる頃(7年後)、娘が高校生になる頃(8年後)、世界はどうなっているでしょうか?
おそらく、AIを使えることは「パソコンが使える」と同じレベルの基本スキルになっているはず。就職活動でも「AI活用スキル」が当たり前に求められているかもしれません。
その時、「うちの子はAI禁止で育てたので使えません」では、スタートラインにすら立てない可能性があります。
「でも、AIに頼りすぎて自分で考えられなくなったらどうしよう…」と心配な方へ:その気持ち、本当によく分かります。でも考えてみてください。電卓を使えるようになっても、数学的思考力がなくなったわけではありませんよね。道具は道具として使いこなし、本質的な思考力は別途鍛える、というバランスが大切なのかもしれません。
今こそ、あなたの考えを聞かせてください
あなたは、自分の子供に生成AIを使わせますか?使わせませんか?
そして、その理由は何ですか?
私と同じように悩んでいる親御さん、すでに明確な方針を決めている方、子供がいない方でも未来への考えがある方…
ぜひ、コメント欄であなたの率直な意見を聞かせてください。
使わせる派の方へ:
- 何歳から使わせていますか?
- どんなルールを設けていますか?
- 実際に使わせてみて、どんな変化がありましたか?
- 不安に感じることはありませんか?
使わせない派の方へ:
- いつまで使わせない予定ですか?
- その代わりに、どんなスキルを重視していますか?
- 将来、子供が「使えない」ことで困るかもしれない不安はありませんか?
迷っている方へ:
- 何が一番の不安要素ですか?
- どんな情報があれば判断できそうですか?
- 周りの親御さんの反応はどうですか?
正解のない問題だからこそ、みんなで考えることに意味があると思います。
あなたのコメントが、同じように悩んでいる他の親御さんの参考になるかもしれません。そして私自身も、皆さんの考えからたくさんのことを学びたいと思っています。
時代の変化は待ってくれません。でも、一人で悩む必要はありません。
一緒に、この難しい時代を乗り越えていきましょう。
コメントが不安な方へ:匿名でも大丈夫です。「AI賛成派の母」「慎重派の父」のようなハンドルネームでも構いません。大切なのは、みんなで知恵を出し合うことです。
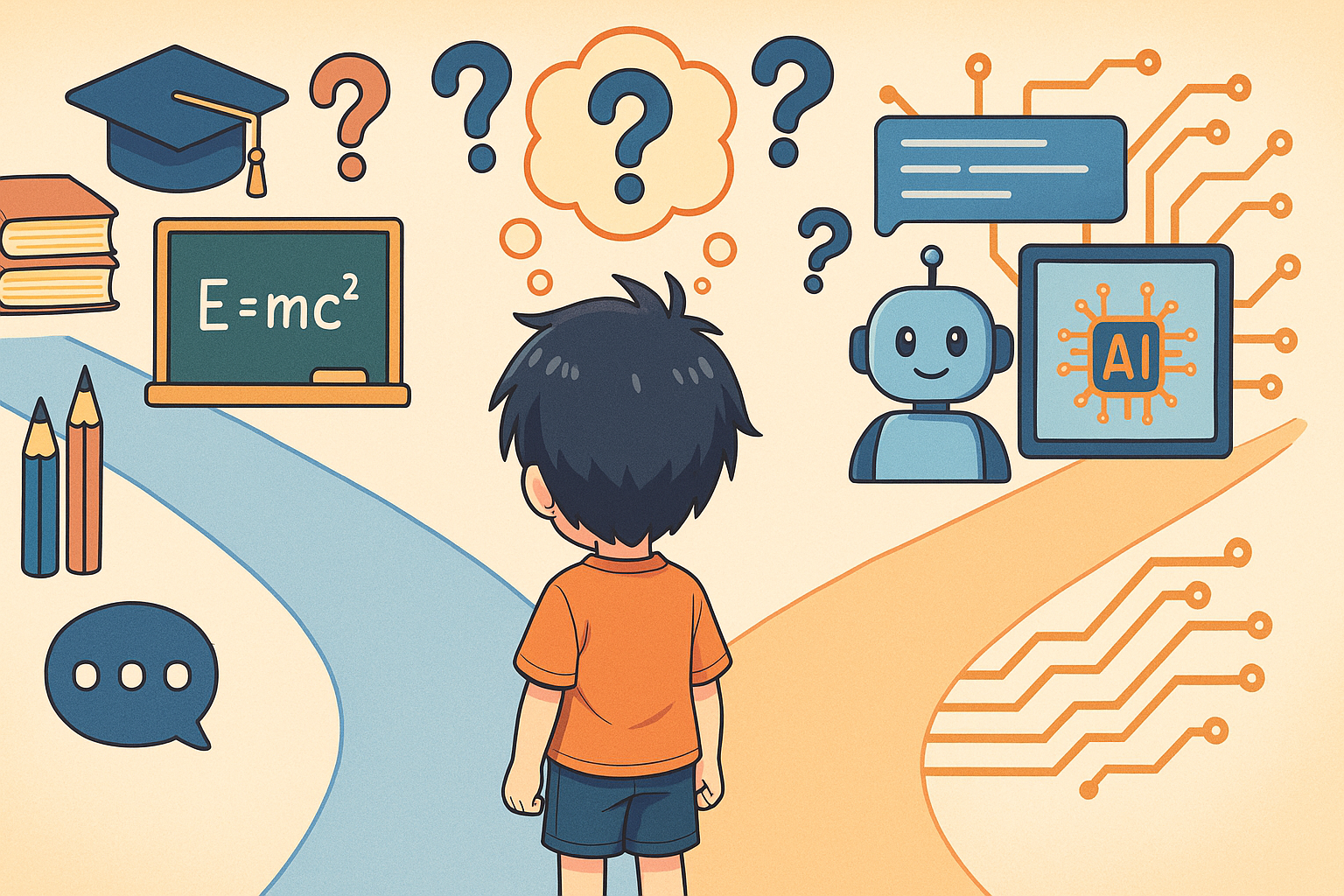
コメント